父が脳梗塞で倒れてからリハビリ病棟を退院するまでに僕が行った手続きをまとめています。
入院費用
入院費用を気にされる方が多いと思うので最初に書いておきますが、個室の差額ベット室を利用していた父は、114日間入院して(一般病棟19日間+リハビリ病棟96日間)、最終的な自己負担額は「570,093円」でした(一般病室を利用していたら最終的な自己負担額は「300,000円」前後)。
| 入院期間 | 窓口負担合計 | 高額療養費の返還 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 114日 | 791,978円 | 221,885円 | 570,093円 |
入院費用の最終的な自己負担額は、「限度額適用認定証の所得区分」「差額ベット室の利用有無」「入院期間」にも影響しますが、数ヵ月入院すると数十万円はかかると思います。
ただ、誰でも利用できる「限度額適用認定証」と「高額療養費」と呼ばれる制度があるので、「年間所得が901万円を超えている」及び「保険適用外の高額差額ベッド室を利用」でもしない限り、100万円以上の高額入院費用がかかることはまずありません。
一般病棟(急性期)
限度額適用認定証の申請
限度額適用認定証を利用すれば、窓口負担を大幅に減らすことができます。
高額療養費の申請でも、払いすぎた分は約3ヵ月後に返還されるので、最終的な自己負担額は変わりませんが、高額療養費の申請では、支払い時に3割負担の費用を用意しなければいけません。
ひと月の入院費だけで10万円以上の差がでますから、立て替える余裕のない方は、限度額適用認定証の発行手続きをして(申請場所は加入している保険によって異なる)、病院の窓口に提出して下さい。
70歳以上の方は基本的に申請不要ですが、住民税非課税等の低所得者は申請が必要です。
手続きは家族の方でもできます。入院が決まったら早めに申請して病院の窓口に提出して下さい(マイナンバーカードの健康保険証利用なら限度額適用認定証の準備は不要)。

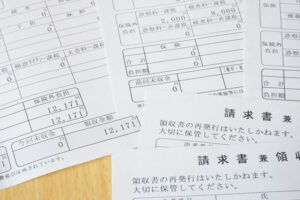
転院先のリハビリテーション病棟を決める
後遺症が残っている方は、2ヵ月以内にリハビリテーション病棟に転院することになります。
医療ソーシャルワーカーから、リハビリテーション病棟のリストを渡され、転院の説明があると思いますが、転院先のリハビリテーション病棟は、患者と家族で決めなければいけません。
これから数ヶ月お世話になる病院です。妥協せず、「自宅からの距離」「スタッフの人数」「1日のリハビリ時間」「個室(差額ベッド室)の有無」等を調べ、必要なら見学して決めて下さい。
この際、面談日や病室の空き等の都合で、転院の許可が出てもすぐに転院できない可能性があります。家族の方はできるだけ早め早めに行動して、必要な手続きを済ませて下さい。
また、転院が決まったら介護タクシーの予約手続きも忘れないで下さい。


リハビリテーション病棟(回復期)
要介護認定の申請
リハビリテーション病棟入院中に後遺症が残っている方は、要介護認定の申請を行います。
申請時期は病院スタッフから説明されると思いますが、どんなに遅くても退院40~50日前までには申請して下さい(申請してから結果が出るまでに約30日かかるため)。
申請が遅れると、ケアマネの契約や介護保険を利用した住宅改修が遅れます。
ただ、後遺症がほとんど残っておらず(退院後も脳梗塞発症前と同じ様に生活を送れる)、早期退院できる様な場合は、介護認定を受ける必要がない可能性もあります。
患者の容体にもよるので、分からない時は病院のスタッフに確認して下さい。

ケアマネジャー(ケアマネ)を決める
ケアマネジャーは、リハビリテーション病棟退院前(遅くても10日以上前)に決めて下さい。
要介護認定申請後なら、結果が出る前でもケアマネジャーと契約することはできます。
本来、介護保険はリハビリテーション病棟退院後からしか使えないのですが、退院後に必要な福祉用具の貸与・購入と住宅改修には使うことができます。また、入院中にケアマネを決めておかなければ、退院後すぐに介護サービスを利用することができません。
時期がこれば、病院スタッフから居宅介護支援事業所のリストを渡されますから、「所在地」「所属するケアマネの人数」「事業所の併設状況」を参考に、居宅介護支援事業所(要支援は地域包括支援センター)に連絡して下さい。後日、ケアマネと面談して契約します。お金は一切かかりません。
介護保険施設へ入所される場合は、その施設のケアマネジャーと契約します。

必要な福祉用具の貸与・購入と住宅改修の契約
在宅復帰する場合は、福祉用具の貸与・購入と住宅改修が必要になる可能性があります。
この際、工事着工許可は申請書提出日から10日程度を要するので、工事が必要な場合は、遅くても退院10日以上前には住宅改修の契約をしておく必要があります(工事は許可が下りてからしか着工できないため)。
- 病院スタッフ・改修業者と自宅を下見
- 必要なものを話し合う
- 見積
- 契約
- ケアマネが市に申請
- 工事・福祉用具の搬入
手続きが遅れると、退院までに住宅改修が間に合いません。


退院後(維持期)
身体障害者手帳の発行手続き
脳梗塞で後遺症が残った方は、発症から6ヵ月後に「身体障害者手帳」の交付申請ができます。
認定を受ければ、医療費の助成や税金の控除・免税等、様々なサービスを受けることができます。
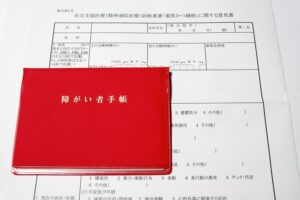

確定申告(医療費控除)
退院後になるとは限りませんが、年間(1月1日~12月31日まで)の医療費が10万円を超えた場合、確定申告(2月16日~3月15日)で医療費控除を受けることができます。
所得から医療費を差し引いて税金を軽減できる制度です。
但し、任意で加入している保険から給付金を受け取っている場合は対象外になる可能性が高いです。

よくある質問
体験談を元に個人的に気になりそうな疑問をまとめてみました。
- リハビリでどれぐらい回復しますか?
-
人それぞれです(恐らく断言できる人はいない)。
参考までに、僕の父は入院当初は左足が完全に麻痺しており、一人で立ち上がることもできなかったのですが、リハビリ病棟退院時には、杖なしで歩行できるまで回復していました。現在は杖を使って歩いていますが、最低限の日常生活は遅れています。
発症後6ヵ月経過しないと身体障害者手帳の発行手続きができないことからも分かると思いますが、脳梗塞はリハビリで症状が大きく改善します。患者の方はリハビリを頑張ってください。家族の方は患者がリハビリに専念できる様サポートして下さい。
- 限度額適用認定証は必須なの?
-
必須ではありません。
高額療養費の申請でも払いすぎた分は3ヵ月後に返還されるので、最終的な自己負担額は同じです。また、クレジットカードで支払って、高額療養費で返還してもらった方がお得になる場合もあります。
先に減らしてもらうか、後から返してもらうかの違いです。
但し、3ヵ月入院すれば数十万円の差がでます。立て替える余裕のない方は、限度額適用認定証の利用をおすすめします。
- 転院する時に介護タクシーは必要なの?
-
必須ではありません。
ただ、車いすが必要な場合や歩行が困難な場合は、専門の介護タクシーを使った方が安心です。
- 入院中のリハビリ装具に保険は適用されるの?
-
条件を満たせば保険が適用されます。
下記の記事で詳しく解説しているので参考にしてみて下さい。
あわせて読みたい 入院中に購入したリハビリ装具の自己負担額と高額療養費制度 入院中に購入したリハビリ装具の自己負担額と高額療養費制度についてまとめています。 リハビリ装具の購入と医療費返還手続き 今回は脳梗塞で入院中に162,020円のリハビ...
入院中に購入したリハビリ装具の自己負担額と高額療養費制度 入院中に購入したリハビリ装具の自己負担額と高額療養費制度についてまとめています。 リハビリ装具の購入と医療費返還手続き 今回は脳梗塞で入院中に162,020円のリハビ... - 家族カンファレンスって何?
-
患者本人・家族・医療スタッフで話し合いを行う場です。
入院期間にもよりますが、僕の父が入院していたリハビリ病棟では数回行われました。現在の状況や今後について詳しく説明してもらえます。また、分からないことがあれば質問できます。
- 介護認定の結果が出る前にケアマネジャーと契約できますか?
-
できます。
むしろそれぐらい早く行動しなければ、退院後に必要な住宅改修や介護サービスの利用手続きが間に合いません。僕の父も介護認定の結果が出る前にケアマネジャーと契約しています。
地域包括支援センター・居宅介護支援事業所に連絡する時は、介護認定の結果が出る前である事を伝えて話を進めて下さい(担当の看護師におおよその介護区分は判断してもらえます)。
- 差額ベット室(個室)に保険は適用されますか?
-
保険は適用されません。完全自己負担です。
料金は病院や設備によって異なるので、事前に確認しておいて下さい。
父が入院していたリハビリ病棟では、1日2,700円でした。
あわせて読みたい 差額ベッド代は完全自己負担!保険適用外かつ高額療養費制度も使えない 特別療養環境室(差額ベッド室)の利用と料金についてまとめています。 特別療養環境室(差額ベッド室)とは? 差額ベッド室は、療養環境について以下の4つの要件を満た...
差額ベッド代は完全自己負担!保険適用外かつ高額療養費制度も使えない 特別療養環境室(差額ベッド室)の利用と料金についてまとめています。 特別療養環境室(差額ベッド室)とは? 差額ベッド室は、療養環境について以下の4つの要件を満た... - 診断書に保険は適用されますか?
-
保険は適用されません。
また、診断書の料金は医療機関によって異なります。
あわせて読みたい 医療保険の給付金を受け取る際に必要な診断書の料金と発行までにかかる期間 医療保険の給付金を受け取る際に必要な「診断書」の料金と発行までにかかる期間をまとめています。 診断書は任意で加入している保険の給付金を受け取る際に必要になりま...
医療保険の給付金を受け取る際に必要な診断書の料金と発行までにかかる期間 医療保険の給付金を受け取る際に必要な「診断書」の料金と発行までにかかる期間をまとめています。 診断書は任意で加入している保険の給付金を受け取る際に必要になりま... - 退院する時にお礼は必要ですか?
-
任意です。
受け取ってくれるところもあれば、断られるところもあります。
事前に院内やパンフレットに「職員に対するお心遣いは不要」等の記載がないかも確認しておいて下さい。渡すのであればスタッフ皆で分けられる菓子折りが無難です。
断られた時は無理強いせず引き下がって下さい。
あわせて読みたい 病院を退院する時にお礼の菓子折りやギフト券は受け取ってもらえるのか? 脳梗塞で病院を退院する時のお礼についてまとめています。 あくまで僕の体験談です。病院によって対応は異なるので参考程度に読んで下さい。 退院する時のお礼について ...
病院を退院する時にお礼の菓子折りやギフト券は受け取ってもらえるのか? 脳梗塞で病院を退院する時のお礼についてまとめています。 あくまで僕の体験談です。病院によって対応は異なるので参考程度に読んで下さい。 退院する時のお礼について ... - 退院後に車の運転はできますか?
-
都道府県によって対応が異なります。
主治医に相談して下さい。
あわせて読みたい 脳梗塞になっても車の運転は可能!?対応は都道府県によって異なるので要注意 脳梗塞で後遺症が残った時の車の運転についてまとめています。 脳梗塞と車の運転について 警察署及び自動車講習センターでは、一定の病気等に関する方の「運転適性相談...
脳梗塞になっても車の運転は可能!?対応は都道府県によって異なるので要注意 脳梗塞で後遺症が残った時の車の運転についてまとめています。 脳梗塞と車の運転について 警察署及び自動車講習センターでは、一定の病気等に関する方の「運転適性相談...
最後に
入院中の患者にはできないことがたくさんありますから、必要な手続きは家族の方が代わりに行って下さい。家族がやるべきことは、患者がリハビリに専念できる様に全力でサポートすることです。
最後に、要介護認定の申請をしてケアマネと契約すれば、その後はケアマネが強い味方になってサポートしてくれます。分からないことは、知識と経験が豊富なケアマネに相談して下さい。


コメント