脳梗塞で入院した時に要介護認定を申請するタイミングと手続きの流れをまとめています。
要介護認定の申請
脳梗塞の場合は、40~64歳(第2号被保険者)でも認定を受けることができます。
| 詳細 | |
|---|---|
| 申請場所 | 市役所(介護保険課窓口) |
| 申請に必要な物 | 要介護認定申請書 介護保険被保険者証(65歳未満は医療保険の被保険者証) 家族の方の身分証明書(家族の方が申請する場合) 申請者の印鑑(同居家族以外の方が申請する場合) |
申請時期
要介護認定の申請は、必ず退院前(入院中)に行って下さい。
退院前に要介護認定を受けなければ、ケアマネジャーとの契約や介護保険を利用した住宅改修が遅れてしまいます。また、退院後すぐに介護保険サービスを利用することができません。
ただ、後遺症がほとんど残っておらず(退院後も脳梗塞発症前と同じ様に生活を送れる)、早期退院できる様な場合は、介護認定を受ける必要がない可能性もありますから、事前に必ず担当の看護師に相談して下さい。看護師の方がどの介護区分に認定されるのかも大体判断してくれます。
父の場合は、リハビリ病棟の家族カンファレンスで、担当の看護師に「そろそろ要介護認定の申請を行って下さい。」と言われたので、市役所で要介護認定の申請を行いました。
申請手続きが終わると、「訪問調査」が行われます(市の職員が病室にやってくる)。
調査日時はある程度指定できますが、2~3週間かかることもあります。また、訪問調査には40~90分程度の時間がかかります(最低でも20~30分はかかる)。
訪問調査の日程が決まったら、市の職員が病室に訪問調査に来ることを病院側に伝えておいて下さい。
必須ではありませんが、正確な情報を伝えるために家族の方も同伴することをおすすめします。
ちなみに、僕は父が一般病棟(急性期)に入院している時に申請しようとしたのですが、市役所の方に「今訪問調査をしても、リハビリ病棟退院前に再度訪問調査が必要になるので、できればその時に申請してほしい。」と言われました。早すぎると二度手間になってしまうので注意して下さい。
申請場所
市役所の「介護保険課窓口」で申請できます。
他にも、「地域包括支援センター」「委託介護支援事業者」「介護保険施設」でも申請可能です。
申請に必要な物
要介護認定申請書は、申請場所で受け取り記入します。
この際、申請書に「主治医の名前」「病院名」「病院の住所」を記入しなければいけないので、事前に調べておいて下さい。申請にかかる時間は10~15分程度です。
調査を受けるにあたって注意すること
調査の結果で「介護区分」が決まり、介護区分が高いほど介護サービスを利用した時の支給限度額が増えます。
| 介護区分 | 限度額(月額) |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
また、要支援と要介護では受けられるサービスが大きく異なります。
中には、嘘をついて介護区分を上げようとする方もいますが、介護認定審査会では、訪問調査で作成された「基本調査」と「特記事項」の他にも、主治医が作成する「主治医意見書」も照らし合わせて審査されます。
当然、主治医意見書には身体の麻痺・拘縮の部位が記載されています。嘘を言って症状をひどく見せても、意見書と合わなければ、再調査になる可能性もあるので注意して下さい。
訪問調査では、あくまで事実を正しく、具体的に伝えることが大切です。
とは言え、年々要介護認定の判定が厳しくなっているため、家族で口裏を合わせて介護度を高くしようとするケースもあるそうです(病院やケアマネジャーが協力してくれることもあるみたいです)。

申請から審査・判定までにかかる時間
訪問調査が終わると、調査の結果をコンピューターで判定し(一次判定)、一次判定や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で審査・判定します(二次判定)。
認定されれば、数日後に「介護保険負担割合証」が郵便で送られてきます。大事に保管しておいて下さい。
また、判定結果にもとづいて介護区分が決まり、「認定結果通知書」と「保険証」が届きます。
参考までに、父の場合は申請から要介護認定を受けるまでに「35日」かかりました。
| 日時 | |
|---|---|
| 要介護認定申請日 | 2017年08月29日 |
| 要介護認定調査日 | 2017年09月08日 |
| 要介護認定日 | 2017年10月03日 |
| 通知が届いた日 | 2017年10月05日 |
要介護認定の効力と有効期間
要介護認定の効力は、申請日にさかのぼります。
認定を受ければ、申請日から認定日までの間に利用したサービスも介護保険の給付を受けることができます。
但し、認定の結果、介護サービスを限度額以上利用していたもしくは非該当の認定を受けた場合は、その分の費用が全額自己負担になるので注意して下さい。
要介護認定の有効期間は市区町村が定めない限り、新規で「6ヵ月」、更新で「12ヵ月」です。
| 有効期間 | |
|---|---|
| 新規申請 | 6ヵ月 |
| 区分変更申請 | 6ヵ月 |
| 更新申請 | 12ヵ月 |
また、認定の有効期間の満了後においても要介護・要支援状態に該当すると見込まれる場合は、認定の有効期間の満了の日の「60日前」から認定の更新の申請をすることができます。
最後に
要介護認定を受けたら、要支援1・2の方は地域包括支援センター、要介護1~5の方は居宅介護支援事業所や介護保険施設のケアマネージャーと契約し、退院前にケアプランを作成してもらいます。
どのようなサービスを使いたいかなど希望や目標を伝え、ケアプランにもとづいて介護サービスを利用します。一部例外を除いて、介護サービスの自己負担は、原則として利用料の1割または2割です。





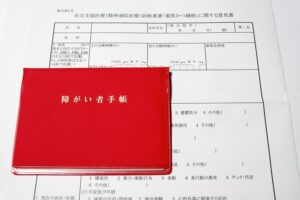




コメント